「NFT」
この言葉、いきなり流行語のように飛び交うようになりました。
この記事ではNFTの初歩について簡単に説明します。
75億円のコラージュ作品
NFTが話題となるきっかけとなったのが、アメリカのアーティスト、ビープルBeepleが製作したデジタル・アートのNFTが今年2021年の3月に75億円で売却されたことでしょう。

もともとこのデジタル・アートは、ウェブデザイナーだったビープルが、練習のため5000日間にわたり1日1作品を制作し続け、それを1つのコラージュ風デジタル作品としてまとめたもの。
それが75億円です。
この作品の芸術的価値が75億円もあったのか、それともNFTというものが革新的だったのか。
NFTは複製できないデジタル・アート?
NFTとはノンファンジブルトークンnon-fungible tokenの略。
日本語では非代替性トークンと呼ばれます。
他と代替することができない、つまり唯一無二のデジタル資産、というような意味ですね。
その名前の印象から、複製が絶対できないデジタルデータ、のように考えている人もいるかもしれませんが、そうではありません。
複製できないのではなく、そのデジタル・アートの所有者が誰であるという<情報>が明確になるのがNFTです。
このブログでは2020年の10月に「NFTが流行りはじめている」として記事を載せていますので、幸らも参考にしてください。
ノンファンジブル非代替の意味
NFTのFはfungibleファンジブルですが、これは代替可能、という意味です。
なのでnon-fungibleノンファンジブルとは、<代替できない>ということになります。
ファンジブルかノンファンジブルかは1万円札で考えれば簡単です。
1万円札にもシリアルナンバーが振ってありますが、1万円札を代金としてももらうときに、いちいちシリアルナンバーは何番ですか?と確認して取引する人はいません。
だからどの1万円札を渡してもOK。
これがファンジブル=代替可能なものということです。
これに対して、1万円札に印刷されている顔にいろんな種類があると想定してみましょう。
たととえば乃木坂46の秋元真夏さんの顔の1万円札が世界に1枚だけあるとします。
私は秋元真夏さんの顔の1万円札しか欲しくない、福沢諭吉や渋沢栄一ではやだ、という場合は、1万円札は他の1万円札では代替できません。
これがノンファンジブルの意味です。
誰が持っているのかをブロックチェーンに記録
ここで、秋元真夏さんの顔の1万円札のデジタル通貨(以下「デジタル真夏札」と呼びます)を作ることを考えましょう。
実物のないデジタル通貨ですから、それをAさんからBさんへ移転するには、何かに記録することによってしかできません。
その記録をブロックチェーンで行うのが、NFTです。
デジタル真夏札をAさんからBさんに移転したとき、デジタル真夏札につけられている固有のシリアルナンバーの所有者は、Aさん所有から、Bさんになった、とブロックチェーンに記入するのです。
ブロックチェーンは簡単に言えば改ざんできないデジタル記録簿です。情報がひとかたまりのブロックになって、そのブロック達がチェーン状につながっているのでブロックチェーンといいます。
もともとはビットコインという暗号資産のために考え出された仕組みです。
NFTは、多くの場合、ビットコインではなく、イーサリアムというブロックチェーンに記録します。
デジタル真夏札を発行し、それをAさんが取得したとき、秋元真夏さんの画像データとAさんが有者者だという情報が一緒にイーサリアムのブロックチェーンに記録されます。
アートのNFTでも一緒です。
アートのデジタルデータ(正確にはリンク情報であるメタデータ)と、誰が所有者かという情報をブロックチェーンに記録しているのがNFTなんです。
複製はできるけど誰が本当の所有者かがわかる、それがNFT
デジタル・アート自体は複製できてしまいます。
最初に挙げたビープルのデジタル・アートも誰でもダウンロードできます。
(※データが重いので、リンクは載せていません)
でも、NFTをみれば(ブロックチェーンを見ればということ)、そのデジタル・アートはAさんのものだ、と誰でもすぐわかってしまうのです。
ただしデジタル情報の場合、「所有権」という概念は日本の法律上はありません。アートNFTをあなたが購入し、ブロックチェーンにあなたの名前(アドレス)が記録されても、それをもってそのアートの所有権は私が持っている、とは法律上は言えない、ここがややこしいところです。
このNFTはデジタル・アートのような画像だけではなく、いろんな分野に展開が可能です。
次回に続く。



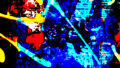
コメント
[…] […]