日銀はインフレ率2%を目標にしていますが、今年(2021年)2月は△0.6%とデフレです。
ではこの2%や△0.6%いうのはどうやって計算しているのでしょうか?
この記事では消費者物価指数について簡単にわかりやすく説明いたします。
インフレは突然やってくる
日銀は国債を買付けるなどの金融政策で、お金の供給量を増やしています。
2021年2月のマネタリーベース(紙幣+硬貨+金融機関が日銀に持っている日銀当座預金)は、対前年比(年平均換算)19.6%増と、2019年の年平均3.6%の5倍以上となっています。
※マネタリーベースについてはこちらの記事を参照してください。
日銀が金融機関から国債を買い取ると、代金を日銀当座預金に振り込むので、この口座残高がどんどん膨らんでいるのです。
このお金の供給量増加で、インフレが突然起こるかもしれないという議論があります。
インフレといっても、日銀が目標としている2%という穏やかなものではなく、10%程度の高インフレです。
インフレとは、モノの価格が上がることですが、これはお金の価値が下がったということ同じです。
1個100円だったチョコが、120円になったということは、チョコの価格が上がったということであるとともに、チョコ1個に対する円の価値が下がったため、より多くの円が必要になった、ということでもあるのです。
貨幣の供給量が増える、つまりお金がたくさんあると、それだけモノの価値に対してお金の価値が下がりやすくなるので、インフレになるかもしれない、と言われるわけです。
2021年2月のインフレ率
では現在の実際のインフレ率はというと、2月は前年同月比で△0.6%とむしろ下がっており、デフレです。
これはマネタリーベースがいくら増えたといっても、金融機関のお金が増えるだけで、企業や家計は消費を増やしたりしていないからだとされています。
買う人がいなければ、いくらお金の量を増やしてもモノの価格は上がらないわけです。
ですが、特定の分野については価格が上がっている、それも大きく上昇しているものがあります。
ペットの価格は急上昇している
たとえばペット。
子犬の価格が軒並み上昇しています。
ペットショップで見かける値段を見ると、数年前の2倍以上になっている感覚があります。
これはコロナ禍によりペット需要が増えたこと、動物愛護法が改正されブリーダーにとってコスト増となったことなどが挙げられます。

子犬に限らず熱帯魚なども値段も30~40%上がっています。
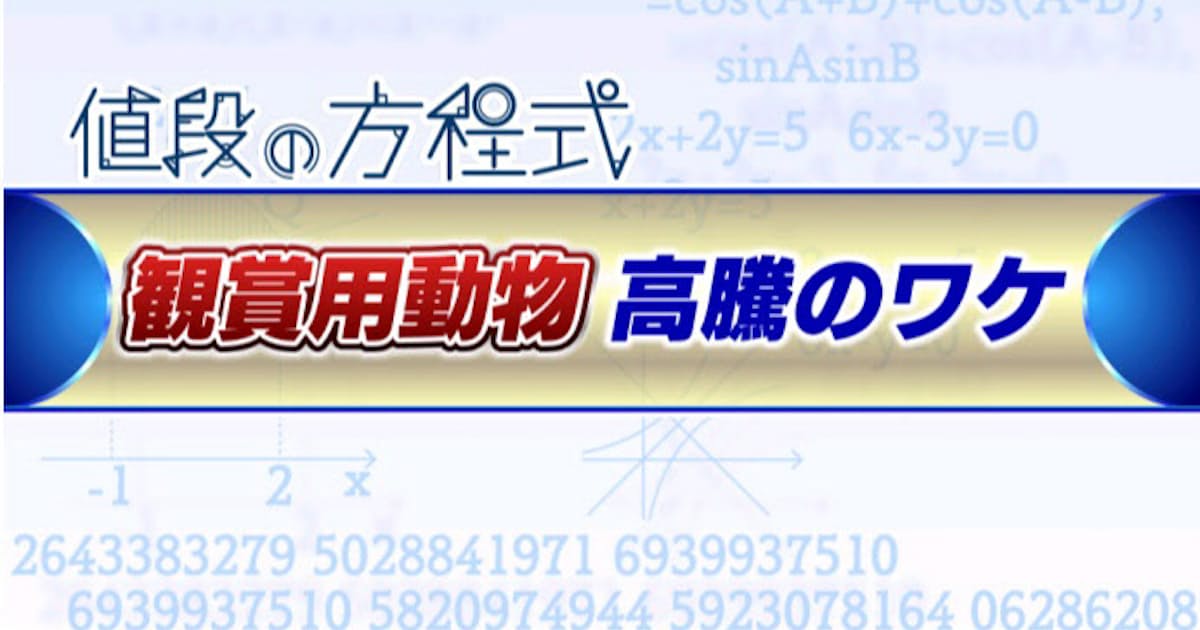
熱帯魚価格の上昇はコロナ禍による輸送コスト増加が一因となっています。
需要が増えているのに、そのタイミングで供給側のコストがあがったりすれば、ペットのように一気にインフレとなることも現実的になってきます。
ではそもそもデフレ△0.6%とか、インフレ目標2%とかの、△0.6%とか2%という数字はいったい何をもとにした数字なんでしょうか?
消費者物価指数
インフレ2%、デフレ△0.6%という物価の数字は、消費者物価指数という数字を用いています。
消費者物価指数とは、英語ではCPI:Consumer Price Indexと表記され、ある年の物価を100として、今はどれだけになるかを示す指標です。
2021年2月現在、基準年は2015年です。
2015年の物価を100として、それに比べて今はどれだけになっているかを示しています。
ではさきほどのペットの価格は、この消費者物価指数に影響を与えるいるでしょうか?
品目に何を選ぶかが重要
子犬や熱帯魚などの価格は、消費者物価指数には反映されません。
すべての商品の価格を調査して消費者物価指数とするのが理想でしょうが、現実的ではありません。
そこでよく消費される品物をピックアップして、その価格を市町村などが調べて集計しています。
現在は585品目です。
1家族が一定期間で消費するような商品やサービスをひとまとめにして、その価格を基準としています。
いろいろな品目をひとまとめにすることを、バスケットと呼びます。
このバスケットの中身は、いちご、マヨネーズ、ノートパソコン、クリーニング代など、一般家庭がよく使うものです。
ペットフードは含まれますが、ペット自体は含まれません。
ペットが入っていたら、消費者物価指数はどうなっていたでしょうか。
ペットのようにバスケットの中身に何を選ぶかによって、消費者物価指数の数字自体が変わってきてしまうおそれがあるのです。
現実にアメリカでは、品目が不適切でインフレ率が1%高く見積もられているという指摘があり、品目を変更した歴史があります。
たった1%と思われるかもしれませんが、消費者物価指数における1%というのは、中央銀行の金融政策を大きく転換させる可能性もあるほど影響力のある1%です。
ですから日本でも5年に一度品目を変更しています。
次回の変更では固定電話が除かれ、その替わりにドライブレコーダーが入る予定です。
時代の変化に対応するのは難しい
ただ同じ商品でも、中身が全く変わらないものというのは意外と少ないですから、昔と今の値段を比べるのは難しいことです。
たとえば家電は高機能化しています。
今のノートパソコンの性能は、私が大学生ぐらい(平成元年直前)のときのスーパーコンピュータよりも性能がいいとも言われます。
さらに商品の値段は下がっているんだけど、実質的にはインフレになっている、という不思議な商品もあります。
たとえばマヨネーズとか、インスタントコーヒー、バター。
これらの商品の値段は昔に比べて下がっています。にもかかわらずインフレになっていることのカラクリは、「減量インフレ」です。
中身の量を減らして、値段はさほど下げないことで、実質的に値段を上げることを「減量インフレ」と呼びます。
減量インフレが可能となったのは、小さな容量のモノの方が売れるためです。
小分けしたほうが売れるため、容量を減らし、でもさほど値段は下げない戦略が成り立つのです。
つまり商品の値のつけ方も時代で変わっているわけです。
消費者物価指数は、このような時代の変化に追いつくためにアップデートを繰り返す必要があります。




コメント