みなさんは本は紙で読んでしますか?それともタブレットとかKindle?
小中学校でのPC、タブレット導入が進んでいます。
これに伴い、デジタル教科書がいいという人と、教科書はやっぱり紙がいいという人の間で論争も勃発しています。
紙の本と電子書籍・デジタル教科書のメリット・デメリットについて解説します。
GIGAスクール構想
日本は「GIGAスクール構想」というものをもっていて、小中学校にPCやタブレットを一人一台配布し、デジタル教科書を2025年度までに100%普及させる目標を立てています。

ITの急激な発達で今の子供達が大人になる頃にはどういう社会になっているかわからない。
このため子供に必要な知識としてICTが必須だという考えにGIGAスクール構想はもとづいてします。
ICTとは、Information & Communication Technologyの略で、情報通信技術のことです。
IT:Information Technologyは情報を処理することに重点を置いた言葉に対して、ICTはそこに通信=コミュニケーションの視点が入っているんです。
つまり、紙の教科書を使いながら先生が教壇の上に立って喋るという古代から変わっていない授業のあり方を、ICTを利用し革新する、というのがGIGAスクール構想の目的です。
生徒はただ単にPCやタブレットで教書を読んでいるわけではありません。
教室の前に置かれた大型モニターに自分の書いた課題や質問に対する解答が映し出されます。
生徒達はそのモニターを見ながら活発に議論を交わすという教材も多く採り入れられています。
また、学力格差が広まっていることから、一斉学習から個別学習にという流れもでもあります。
でも本はやっぱり紙がよくない?
ICTの重要さを否定する人はいませんが、教科書をすべて電子にしてしまうことには反対論が根強くあります。
PCやタブレットをみすぎることによる健康被害も懸念されます。
自宅学習する際の家庭の通信環境に差が出るという不安もあります。

ではここで紙の本の良さを考えてみましょう!
・全体をざっと見たり、復習がしやすい→どこに書いてあたっけ、がイメージつきやすい
(電子は分量の感覚がイメージできない)
・書棚に置いてあると今まで学んだことがすぐわかる
・自分が学んだことの厚みがわかる
紙の本のデメリットも考えてみましょう!
・分厚い重い、持ち運びに困る
・保存場所に困る
・リンクによる参照ができない
電子書籍・デジタル教科書はこんなことができる!
では逆に、電子媒体の本の良さを挙げてみましょう。
・リンクですぐに専門用語の説明などが読める
・どこにでも持ち運べる
・いつでも新しい書籍が買える
デジタル教科書だけのメリットも考えておきましょう。
・全員がICTでつながることにより、他の人の意見や考えがわかり、よりコミュニケーションを重視した学び方ができ、生徒全員が参加した授業が可能になる
(今までは手を挙げる積極的な子だけが授業に参加していた)
・文字だけではなく画像や動画を使って何かを表現できることを学べる
では電子媒体の本のデメリットは何でしょう?
・目が疲れる、健康被害が怖い
・リンクがあって関連情報をすぐに見られることは学習にとって障害となる
・動画を用いた教材はワーキングメモリー問題が不安
電子書籍・デジタル教科書はリンクから用語説明や関連情報、さらに画像や動画を表示することもできることが大きなメリットの一つですが、これは逆にその本の理解度を妨げることになるという研究もあります。
注意が散漫になることが原因です。
たとえば夏目漱石などの古典小説を読んでいるときも、注釈をいちいち読みながらだと物語に没頭できませんよね。
何かを理解するためには、なるべく一点のことだけに集中し、それ以外のことは後回しにするのがいいということです。
(「Reading Hypertext and the Experience of Literature」David S. Miall and Teresa Dobson)
ワーキングメモリー問題というのは、動画教材についての問題です。
ワーキングメモリーとは、短い時間に頭の中で情報を処理する能力のことです。
動画は情報量が膨大なので、動画を見ながらの勉強はこのワーキングメモリーがいっぱいになってしまい、能動的に考える余裕がなくなるといいます。これがワーキングメモリー問題です。
私の使い方:紙とデジタルの併用が理想か
上の解説でGIGAスクール構想は、デジタル教科書を2025年度までに100%普及させる目標があると書きましたが、これは2025年にすべての教科書が紙に置き換わる、という意味ではありません。
すべての教科書にデジタル教科書版が用意されている、という状態にすることです。
私自身の使い方を紹介しておくと、
・経済学の理論など難しい内容の本は紙
・小説は電子書籍(Kindle)
・あまりにも分厚くて読むのに躊躇するような本(たとえばユヴァル・ノア・ハラリの「ホモデウス」など)はオーディオブック(Audible)
・ピンポイントでここを勉強したい!というときはYouTube動画
と媒体を使い分けています。
このやり方は自分的にはベストな勉強方法だと確信していますが、どれか一つ、ではなく、使えるメディアはそれぞれのメリットに合わせて全部使う、それがいいのは当然でしょう。
紙、電子の使い分け具体例
理論を学ばなければならないような本は、書き込んだり、付箋を貼ったり、前の章に戻って読み直したり、逆に先の章に何が書かれているのかをみながら読んでいったりしますから、物理的な紙の方が圧倒的に使いやすいです。
これに対して小説のように、順々に読んでいくものは、電子書籍(Kindle)の方が気楽に読めます。
さらに見逃せないのがオーディオブック(アマゾンのAudible)です。
私は1.6倍速で聴いていますが、こうすることで細かい点やわからないことはすっ飛ばして、本全体の概略がスムーズに入ってきます。
特に電車の中はこれを使い始めるとむしろ楽しくなります。電車の中でゲームをするのがもったいないと思うようになるほどです。
そして最後にYouTube。
今何かを学びたいときに、いろんなYouTube動画がアップされています。
たとえば微分。
経済学では微分が必ず出てきますが、そもそも微分って何のためにあるんだっけ?と基本的なことがわからなくなることがあります。
そこでYouTubeです。
微分ならヨビノリ『予備校のノリで学ぶ「大人の数学・物理」』がお薦め。もう有名ですから皆さんもご存じかと思います。
意外と少ない日本の教育費
デジタル教科書問題も、紙とデジタルをうまく組み合わせて使うことが重要かなと思います。教科書代が増えてしまうなど費用の問題はあるかもしれませんが、それこそ国だけではなくみんなで解決すべきことでしょう。
それに日本は他国に比べると教育に意外とお金をかけていません。
GDPに占める教育費(公的支出と家計の支出の合計)の割合をみると、日本は5.0%とOECD平均5.7%より下です。アメリカ、韓国などは7%を超えています(2009年、文部科学白書より)。
教育は将来の経済に大きく関わります。教育費については中途半端ではなく、惜しみなく出すことが大切でしょう。
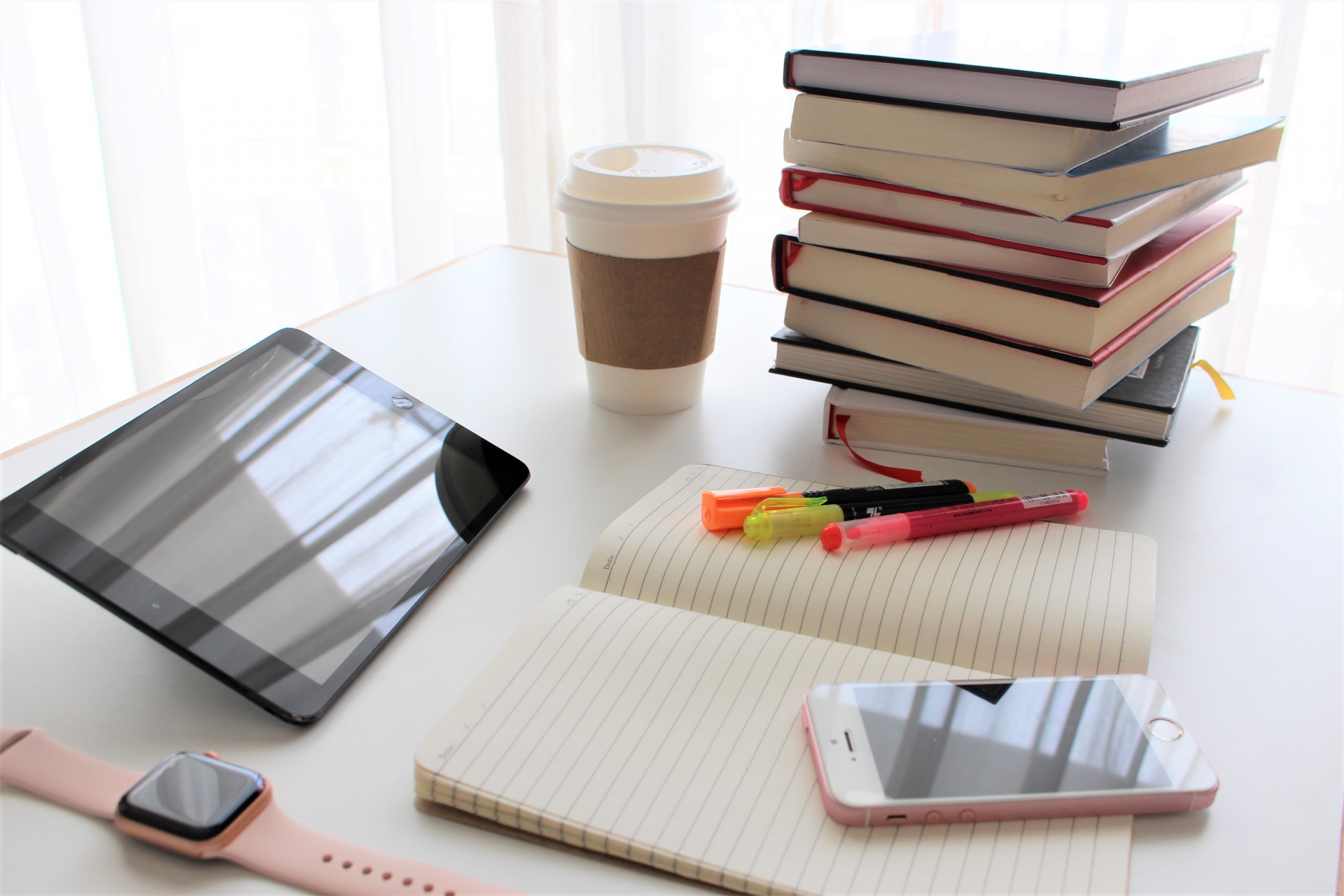


コメント