OECDや世界銀行の発表では、今年の世界経済は5%~6%ぐらいのマイナス成長だと予想されています。
これは戦後最悪の状況です。
日本政府はこの状況に対処するために、230兆円規模の経済対策を行うことを決定しました(参照:「事業規模 233.9 兆円・新型コロナ対策予算の解剖」第一生命経済研究所)。
こんな時だからこそ、お金と経済の関係を正しく学んでおくことが大切です。
今回はお金のうち特に、<紙幣>について解説します。
※この記事は主に「現代経済学の直観的方法」(長沼伸一郎著)を参考にしています。
紙幣の始まりは預かり証だった!?
近代的な紙幣は、18世紀初頭のイングランドが最初と言われてします(それ以外にも事例はありますが、広く普及したのはイングランド)。
この紙幣、最初は金(Gold)の「預かり証」から生まれたものだったのです。
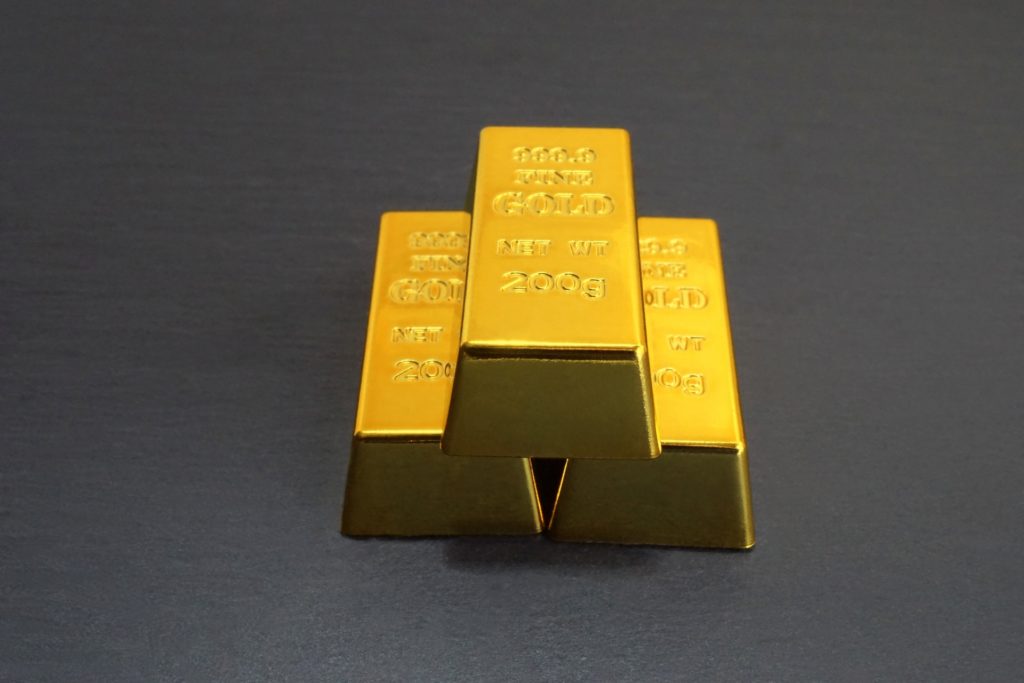
少し前の16世紀、金(Gold)は当時、どこでも使える共通通貨でした。
しかし、その時代のイングランドは(カトリックとプロテスタントが争っていて)治安が悪かったといいます。治安が悪いので金(Gold)を持ち歩いたり、家に置いておくのは危ない。
そこで頑丈な金庫がある専門の業者を預けて、「預かり証」を発行してもらうということが一般化しました。
専門業者といっても貸金庫屋ではなく「金細工士」でした。金細工士は金(Gold)を大量に使うため金庫を保有していたのです。
この預かり証を金細工士に持っていくと、だれでもそこに書かれている量の金を金庫から引き出してくれます。
しかも預かり証は誰が持っていってもよく、本人確認はありません(16世紀に免許証とか本人確認書類などありませんから・・)。
その預かり証を持っている人が金(Gold)の保有者だとされて、金細工士は金(Gold)を引き出してくれるわけです。
預かり証を他人に渡したら?
今、あなたが1㎏の金を預けて預かり証をもらったとします。
その後、一軒家を建てて、その代金がちょうど金1キロでした。
あなたなら、どのようにして代金を支払いますか?
わざわざ業者から金を引き出さなくても、預かり証を渡してしまえば払えますね。
金は重いですし、何より引き出すのは危険ですから、わざわざ引き出して金(Gold)で払うより、預かり証をそのまま渡してしまった方が安心です。
これが紙幣の始まりです。
この預かり証が紙幣のように市中で流通していったのです。
そしてこの預かり証の流通するにつれて、奇妙な現象が生じました。
その現象が、資本主義経済の源ともなる紙幣の重大な機能となります。
金細工士が儲け話にのったら何が起きる?(信用創造)
もともとの金1㎏は金細工士の金庫にあります。市中では預かり証だけが転々流通し、金(Gold )を引出に来る人はほとんどいません。
そこにある貿易商が、毛皮貿易の話を金細工士に持って来ました。北欧から毛皮を買付け、イングランドで販売するという話です。金1㎏を半年貸してくれれば、1.2㎏にして返すといううまい話です。
北欧との取引は金(Gold)でなければできないため、金細工士に話を持ちかけてきたというわけです。
しかもその時の状況からするとその話はかなり確度の高いものだったとします。
その話を信じた金細工士は、貿易業者に金1㎏を貸し出すことにします。
半年後、貿易業者は借りた金1㎏で毛皮を買い込み、無事、金細工士に金(Gold)返還しました。
ここで、おかしなことが起きていると思いませんか?
だって金(Gold)は最初あなたがもっていた1kgしか登場しません。
金(Gold)は1㎏しかないのに、あなたが買った家と、そして貿易商が行った毛皮の買付けという2つの取引が成立したのです。
つまり、金(Gold)の2倍の取引が成立したのです。
こんなことがあっていいのでしょうか?
これは金細工士が金(Gold)を「又貸し」したことから始まります。
このように紙幣のもとの価値よりも多くの取引ができてしまうことを、経済学では貨幣の「信用創造」といいます。
この信用創造は、現代の経済では2倍どころではありません。
その話は後編で。
なお、この民間業者でる金細工士が発行していた金(Gold)の預かり証を、1694年設立のイングランド銀行が追認するような形で紙幣が発展していきました。



コメント
[…] これを信用創造といいます。信用創造の基本については、前編を参照してください。 […]
[…] […]