「貧困女子・子供の貧困の意外な理由 格差社会と相対的貧困率(前編)」で日本の税と社会保険の負担率は、先進国の中では決して高くない! というお話をしました。
それは「社会保険料と税金を足した金額」と「所得」との比率である、国民負担率という数字で分かります。
低い国民負担率
たとえば所得が500万円で、税金と社会保険で250万円支払っていれば国民負担率は50%となります。
日本の国民負担率は42.8%と、フランスの67.2%に比べるとかなり低い数値です。
| 消費税 | 国民負担率 | 相対的貧困率 | |
| フランス | 20% | 67.20% | 8.10% |
| デンマーク | 25% | 66.40% | 5.80% |
| フィンランド | 24% | 63.20% | 6.30% |
| オランダ | 21% | 54.60% | 8.30% |
| ノルウェー | 25% | 51.20% | 8.40% |
| 日本 | 10% | 42.80% | 15.70% |
| 韓国 | 10% | 39.20% | 17.40% |
| アメリカ | 0% | 33.10% | 17.80% |

上のグラフを見てください。
消費税率(青棒線)が低い国は国民負担率(オレンジ棒線)が低いことがわかります。
そして国民負担率が低い国ほど、相対的貧困率(折れ線)が高いのです。
この関係はグラフにすると明かなわけです。
最も極端な例ではアメリカです。
アメリカは消費税(付加価値税)はありません。小売売上税(Sales Tax)※1という消費税に似た税金はありますが、これも州や群などにより税率が異なります。
※1 消費税(付加価値税)は、原料メーカーや製造メーカーも含めたすべての消費に対してかかるものですが、アメリカの小売売上税(Sales Tax)とは、名前の通り、消費者が店舗などの小売業者から消費したときのみ課税されます。
アメリカの国民負担率は33.1%と先進国の中では最も低く、相対的貧困率は17.8%と先進国の中で一番高い数値です。
数字だけ見ると日本はアメリカ型の社会になっていると言えます。
しかし日本はアメリカのように一部の勝者だけが巨万の富を得る社会でもありません。
日本人の富裕層№1は柳井正さん(ファーストリテイリング)で資産総額は2兆3千億円ですが(Forbes日本長者番付2020)、この数字はアメリカではトップ10にも入りません。
にも関わらずなぜ日本は国民負担率が低く、相対的貧困率が高いというアメリカ型になっているのでしょうか?
中間層が貧困になりやすい3つの理由
それは、日本は年収400万円~600万円の人の国民負担率が低いためだといいます。
いわゆる中間層の人の国民負担率が、フランスなどに比べると低いのです。
しかし、多くの人はこれに反論すると思います。
一番割に合わないのは俺たちだ!
そうなんです。
この中間層の人達が一番、税金や社会保険の負担を重いと感じている層でもあると思います。
ではこの感覚と、実際の数値のズレはどこから来るのでしょうか?
それは日本独自の貧困原因が3つあるためです。
この日本独自の貧困原因のために、今まで普通に暮らしていたサラリーマンの人も、いきなり相対的貧困層と同じような生活を強いられる可能性があるのです。
だから中間層の人の負担感が激しいのです。
1.日本独特の貧困原因の最初の1つめは、住宅ローンです。
住宅ローンは、30年~35年ローンというもの凄い長い期間のものが普通です。
そして日本の住宅は高い!

中間層である年収500万円の人も、多くは5,000万円ぐらいの家を購入し住宅ローンを組みます。
この場合、年収の10倍になります。
ところがアメリカでは(ニューヨークなど一部地域を除けば)、25万ドルもあれば家を購入できますから、同じ所得でも5倍に過ぎません。
日本の中間層は倍の負担を強いられているわけです。
35年もの間、倍の負担を受け続けるのは、しんどい。
入社して定年まで同じ会社で勤め上げるのが普通だった「日本的経営」の時代であれば35年ローンも問題なかったでしょうが、時代は変わりました。
年収の10倍ローン×35年間というリスクは、日本的経営が崩れた新しい働き方に合わないとも言えます。
しかも内閣府の調査では、日本の持ち家率は88%を超えており、アメリカ67.6%、ドイツ52.1%、スウェーデン55.3%に比べると飛び抜けて高いのです。
土地は必ず値上がりする、だから資産としての家を保有すべきだ、という土地神話に根付いた行動でしょう。
リモートワークが徐々に浸透すれば、この土地神話も崩れる恐れがあります。
住宅ローンについて真剣に考え直すタイミングが来たと言えます。
2.日本独特の貧困原因の2つめは、保険です。
生涯で一番高い買い物はなんといっても住宅ですが、その次に来るのが保険だといいます。
特に日本人は生命保険が大好きで、しかも死亡保険にいろいろな付帯保険がついた複雑怪奇な保険にたくさん加入しています。
日本は国民皆保険であり、公的な医療保険制度の充実は他の先進国に負けません。
にも関わらずそれをさらに上回る保険を保険会社も勧めますし、加入者はなんだかよく分からないけど入っておいた方がよさそうだという感覚で加入します。
日本は災害が多い国ですから、将来に備えておこうという思いが強いのでしょうね。
しかし他国を見ると、アメリカは公的な医療保険制度がないため多くの人が医療保険には入っていますが、生命保険に加入する率は低いといいます。
欧州は日本同様、公的な医療保険制度が進んでいるため生命保険にも医療保険にも入らず、投資信託のような運用商品としての色が濃い貯蓄型保険に入ることがほとんどだといいます。
これに対して日本は、国の社会保険料を支払っているにもかかわらず、さらに民間の複雑な医療保険付の生命保険料をダブルで支払っているのですから、それは負担感が強くなるのは当然ですね。
3.日本独特の貧困原因の3つめは、教育費です。
日本は大学などの高等教育の教育費が高すぎます。
これは国の補助金による負担有合が他の先進国に比べて少なすぎるためです。
大学や専門学校の授業料の自己負担割合は、日本は67%にも上ります。
これに対して、フランスは16%、ドイツ15%です(出典:内閣府)。
アメリカは66%ですから、ここでもやはり日本はアメリカ型なのです。
アメリカは学生が自分で学生ローンを組んで授業料を支払うケースがほとんどですが、そのローン残高は170兆円にもなります!(出典:東洋経済オンライン)
欧州は大学までほとんど授業料がかからない国が多くあります。
優秀な人材を育てることによってその後に経済を活性化してくれるから、という理念が根底にあるといいます。
これも高い国民負担率がバックボーンにあるからこそできる施策です。
日本も今年令和2年から、大学や専門学校などの授業料について支援を受けられる制度が創設されました(高等教育の修学支援新制度)。
しかしその範囲は住民税非課税世帯に限られ、中間層には支援の手は届きません。
なお住民税非課税世帯の定義についてはこの記事の前編を参照してください。
まとめ
日本は住宅ローン、保険料、教育費という「負担三種の神器」のようなものがあるため、国民負担率がフランスなどに比べて低くてもお金に余裕がなく、特に中間層の負担感が強くなってしまうわけです。
リモートワークなど社会が変わりつつある今、「負担三種の神器」の支出を見直す必要があると言えます。
持ち家は本当に必要か、
保険はもっとシンプルにできないか、
この2点は自分でも見直すことができます。
しかし大学などの教育費は、国民負担率との問題を絡めて国として政策を変えていかなければなりません。
そのためには消費税などの負担を増やすべきだ(OECDの提言では20%~26%)、というのが理論的な結論になりますが、さて皆さんはどう思われますか?


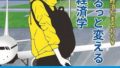
コメント