安倍首相は2020年6月3日、最低賃金の全国平均を1,000円に引き上げる目標を維持すると表明しました(以前から目標としていたのをコロナの問題で経済悪化が予想されるが、その目標は維持するという意味です)。
では2019年の最低賃金の全国平均はというと・・・・、901円です。
東京は1,013円と1,000円を突破していますから、平均額を押し下げているのは・・・
青森、秋田などの東北勢と、佐賀、大分、鹿児島といった九州勢などが、まだ790円なんです。
この辺の地域はまだまだ1,000円に遠いんですね。
この最低賃金の議論で必ず出てくるのが、最低賃金を引き上げるの実はよくない!、という論調です。
これは
最低賃金パラドックス
と呼ばれます。
経済学の入門書にも出てくる問題ですが、
いったい、どんなパラドックスなんでしょうか?簡単に説明したいと思います。
最低賃金引き上げのパラドックス!
最低賃金パラドックスとは、最低賃金をあげると、
若者の失業率が上がってしまったり、
低賃金の人達が真っ先に解雇される、
といった、本来助ける対象であった人達を逆に苦しめることになる、というパラドックス現象を言います。
なぜ最低賃金をあげると若者の失業率が上がったりするんでしょう?
ここでは単純化のために、ファストフード店のフロントスタッフのバイトを想定してみましょう。
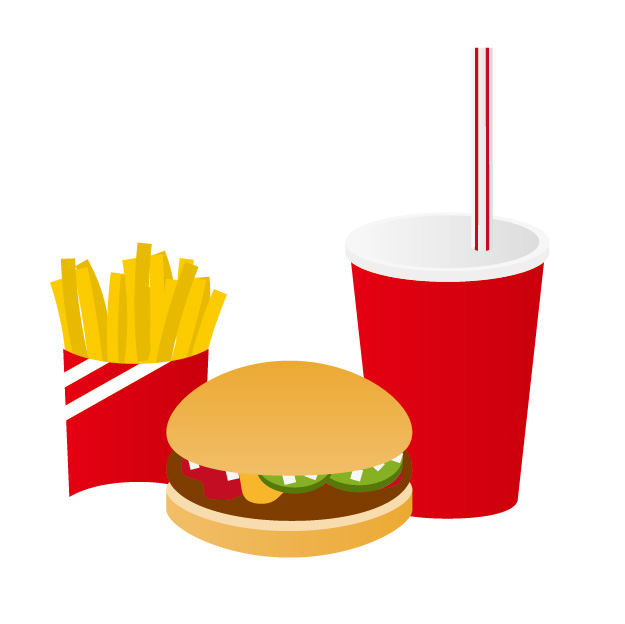
ファストフード店のバイトは単純作業ですから、誰でもできるわけで、未経験者でも高校生でもすぐできる、だから多くは最低賃金に近い水準となります。
では、まだ最低賃金が790円ぐらいの地方で、最低賃金を1,000円に引き上げたら、ファストフード店はどう反応するでしょうか?
固定費はアップしたくない、というのが企業の心情
アルバイト代のような人件費は、売上とは関係なく、一定額が毎月支出される費用です。
このような費用を固定費と呼びます。
売上と関係がない固定費の増加を企業が嫌う気持ちは、誰でも分かると思います。
固定費が上がってしまったら、売上がそれまでとは変わらないのであれば、利益がずっと削られてしまうことになるからです。
しかも最低賃金は法律ですから、この固定費アップは未来永劫続くわけです。
これに対する対策を打たなければなりません。
人員削減が手っ取り早いですが、フロントやキッチン作業にも熟練した人が必要なため、この人達をやめさせるのは、店舗経営的にリスクがあります。
つまり今働いているスタッフをやめさせるにはためらいがあります。
そこで、新しく新人を雇うのをやめるという判断を、お店はします。
新人を雇わない・・・つまり若者の失業率が増える。
という結論になります。
さらに、長期的にはIT導入によるフロント作業の効率化もあります。
たとえばタッチパネル式の注文システムの導入するなどです。
これには初期投資がかかりますが、それは一時的なものなので、固定費を削減できるのであれば長期的にはこちらの方がお得です。
ですから、企業は投資をしてでも徐々に人員を減らそうとします。
減らす人員は、単純作業しかできない新人です。長期的にも、新しい人を雇わないわけです。
こうして、最低賃金を法律で上げると、若者の失業率が上がることになります。
そもそも最低賃金をあげるというのは、こういう単純作業しかできない入門レベルの労働者(これを非熟練労働者といいます)の所得を増やすためです。
非熟練労働者のために最低賃金を法律で上げたのに、所得が増えるどころか、働きたくても働くことができない!、というパラドックスが起きるというわけです。
以上が教科書的な最低賃金パラドックスです。
単純化のためにかなり荒っぽい筋立てとなっていますが、基本構造はこんな感じです。
この最低賃金パラドックスがあるため、多くの経済学者は法律で最低賃金を決めることには反対してきました。
最低賃金を法律で決めるよりも、職業訓練のための教育投資とか、所得が少ない人の税金を安くするなどの施策を推奨する、と多くの経済学の入門書に書かれています。
でもこの最低賃金パラドックは本当に起きるものなのでしょうか?
最低賃金引き上げのパラドックスの実例
最低賃金パラドックスの実例としてよくあげられるのがフランスです。
フランスは先進国の中でも最も最低賃金が高いと言われています。現在は10.15ユーロ、約1,300円です。
ということは、最低賃金パラドックからすると、フランスの若者の失業率も高くなるはずです。
では実際どうなのかというと・・・

2017年の若年層、ここでは15歳~24歳のことを若年層を呼びますが、この年齢の失業率をグラフにすると、確かにフランスは22.16%と日本の4.65%の5倍近い数字となっています。
経済状態が最悪なイタリア、ギリシャに次ぐ高さというのは、確かに意外ですね。
本当に最低賃金パラドックスは存在していた!
でもことはそんなに単純ではありません。
さらなるパラドックスが登場します。
続きは(後編)で。
今回の記事は主に次の本を参考にしています。
「マンキュー入門経済学(第3版)」N・グレゴリー・マンキュー、東洋経済新報社
「米国最低賃金引き上げをめぐる論争」明日山陽子、ジェトロ
「貧困を救えない国 日本」阿部彩/鈴木大介、PHP新書



コメント
[…] この記事は「時給引き上げで失業率が上がる?最低賃金パラドックス(前編)」の続きです。 […]
[…] この記事は「時給引き上げで失業率が上がる?最低賃金パラドックス(前編)」の続きです。 […]